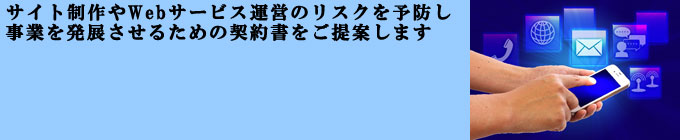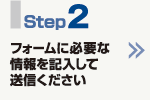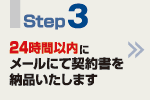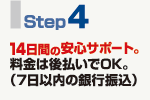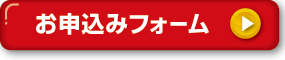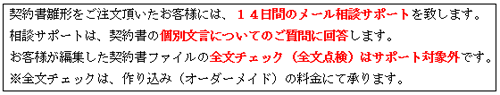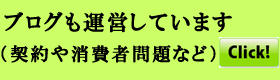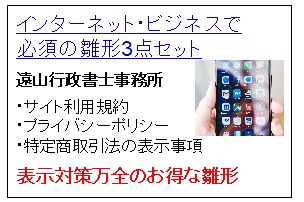経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
日本国内から外国に存在するサーバーにアクセスして表示されるウェブサイト上の表示について、日本の登録商標に基づき商標権侵害を主張できるか?
日本国内のユーザーの要求に応じて外国に存在するサーバーにアクセスして表示されるウェブサイト上の表示であっても、日本国内の需要者に対する商標の使用等といえる表示であれば、日本の裁判所において、日本商標権の侵害に基づく請求が認められることになると考えられています。
以下に具体例について解説します。
(1)日本語のページが用意されているA国の違法コピー・ソフトウェア販売サイトにおいて、違法コピー・ソフトウェアについて、オリジナルのソフトウェアの登録商標と同一の商標を表示して広告されていた場合。
日本語で表示された販売サイトを運営することは、日本国内の需要者を対象とした商行為であるといえます。そこで、オリジナルのソフトウェアの登録商標と同一の商標を表示して広告するのは、日本国内の需要者に対する商標等の使用があったといえます。
その販売する物品が違法コピー・ソフトウェアであるなら、商標権侵害となる可能性は高く、日本の裁判所において商標権侵害に基づく請求が認められる余地は大きいといえるでしょう。
(2)日本への配送料が明記されているB国の高級カバンの販売サイトにおいて、正規のメーカーから仕入れた真正商品について、当該商品の登録商標と同一の商標を表示して広告されていた場合。
一定の要件を満たす商品の並行輸入については、商標の機能である出所表示機能及び品質表示機能を害することは無く、(日本国内の)商標を使用する者の業務上の信用及び需要者の利益を損わないことから、商標権侵害にはあたらないとされています。(フレットベリー事件最高裁判決。最高裁平成15年2月27日第一小法廷判決・判時1817号33頁)
よって、この真正高級カバンの輸入が商標権侵害にあたらないということになれば、当該販売サイト上での広告についても、日本の裁判所において商標権侵害に基づく請求は認められません。
(3)日本の自転車メーカーが自転車の車名について登録商標を行っていたところ、日本円への換算機能が用意されているC国の自転車販売サイトにおいて、D国の自転車メーカー製造の日本未発売自転車について、上記商標登録された自転車の車名と同一の車名を表示して広告されていた場合。
C国の当該サイトには日本円換算機能が用意されており、これは日本国内の需要者に向けた販売を予定しているといえます。したがって、日本国内の需要者に対する商標の使用等があったといえ、日本の裁判所において商標権侵害に基づく請求が認められる可能性は高いといえるでしょう。
(4)日本の宅配専門ピザ・チェーンが商品であるピザの商品名について日本で商標登録を行っていたところ、E国のF市を宅配地域として展開している宅配専門ピザ・チェーンの宅配受付サイトにおいて、特定のピザについて、上記商標登録された商品名と同一の商品名を表示して広告されていた場合。
宅配地域が外国の特定の市に限定されているうえ、宅配ピザという商品の特性上、日本への輸出は考えにくく、日本国内の需要者に向けた商標の使用等にはあたりません。
したがって、日本の裁判所において商標権侵害の基づく請求は認められず、そもそも国際裁判管轄が認められないとして、訴えが却下される可能性も高いといえるでしょう。
(5)日本の自動車メーカーが自動車の車名について商標登録を行っていたところ、ヨーロッパのG国の自動車ディーラーのウェブサイトにおいて、小型大衆車について、上記商標登録された車名と同一の車名を表示して広告されていた場合。なお、当該小型大衆車は、G国から日本にも輸入されているものの、日本では別の車名で販売されていた。
ヨーロッパの自動車ディーラーの商圏は、ディーラーの所在地に限定されるのが一般的であり、大衆車を日本へ輸出して販売するのは今日の経済情勢ではメリットが少なく、日本での販売を想定しているとは考えにくいと判断されます。このことから、当該ウェブサイトは、日本国内の需要者に対する商標の使用等をしているとはいえません。
したがって、日本の裁判所において商標権侵害の基づく請求は認められず、そもそも国際裁判管轄が認められないとして、訴えが却下される可能性も高いといえるでしょう。
問題の所在
商標権等の知的財産権は、一般に権利が成立した国内においてのみ有効とされています(属地主義の原則)。一方、インターネット上では、日本国内にサーバーが存在しなくても、日本国内の需要者に対して、他人の商標を使用して商品の販売やサービスの提供を行うことができます。
そこで、日本国内にサーバーが存在しない場合であっても、日本法が適用されるのか(準拠法)、日本商標権の侵害があるといえるのか(商標法の解釈)が、それぞれ問題となります。
また、実際に訴えを提起するにあたり、例えば侵害者が外国法人であった場合に、日本の裁判所に訴えが提起できるのか(国際裁判管轄)も問題となります。
国際裁判管轄
日本国内にサーバーが存在しない場合であっても、侵害者が日本に住所等を有する自然人である場合や日本の法人等である場合には、日本の裁判所に国際裁判管轄があるとされています。(民事訴訟法第3条の2第1項、第3項)
また、侵害者が外国の法人等である場合であっても、日本国内に主たる事業所が存在する場合には、日本の裁判所に国際裁判管轄があるとされています。
上記のいずれにも該当しない場合でも、ウェブサイトでの商標使用行為が日本国内での使用といえるなら、不法行為の発生地が日本国内であると解釈でき、日本の裁判所に国際裁判管轄があると考えられます。
準拠法
商標権侵害に基づく損害賠償請求は、不法行為に基づく請求と考えられ、通則法第17条では、不法行為の損害賠償請求の準拠法は、原則として「加害行為の結果が発生した地」としています。
ウェブサイトでの商標使用行為が日本国内での使用といえる状態であれば、日本国内で商標権侵害という結果が発生したということができ、日本法が準拠法となると考えられます。
商標権侵害に基づく差止請求については、通則法には直接の規定はありません。しかし、当該商標権と最も密接な関係がある国であることが確認されれば、日本法が準拠法となりうる可能性はあります。
商標権侵害
商標権等の知的財産権については、「属地主義の原則」があり、日本商標権の侵害を成立させるためには、日本国内において当該商標の使用があったことを証明しなくてはなりません。
そのためには、外国の当該ウェブサイト上での商品やサービスの提供が、日本国内の需要者を対象としているという事実が必要になります。当該ウェブサイトにおいて、日本語で当該商標を使用し販売行為をしているのが明白な場合や、代金の表示が日本円であるなど、日本の需要者に訴求している場合には、日本の商標法を適用できる可能性があります。