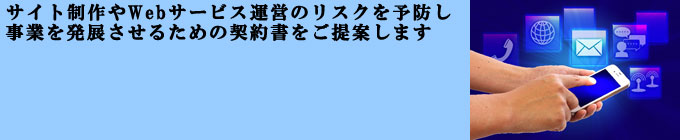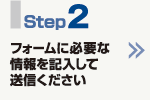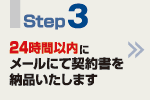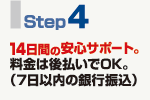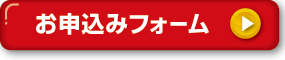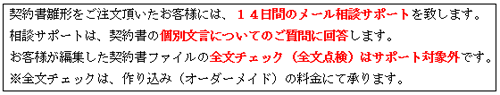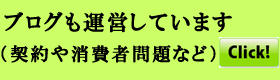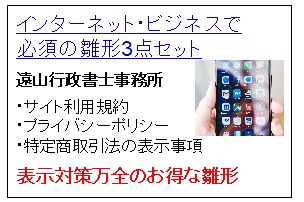経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
インターネット等のオンラインやCD-ROM等のパッケージによって提供されたデータベースから情報やデータを取り出して、これを第三者に提供するなどの利用行為について、何らかの法的な制限があるか?
ここでのデータベースとは、(ア)特定のテーマに基づいて、データを体系的に整理又は整理のつく状態で保存し、(イ)データの集まりの中から必要なものだけを指定して、情報としての部分データとして取り出せ、(ウ)コンピュータ機能を備えている情報端末機器で検索可能な形態になっているものを指します。
データベースから取り出された個々の情報・データ自体に著作物性が認められる場合、それぞれが著作物として保護されます。著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの であって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条1項1号)」とされています。
データベースに著作物性が認められる場合には、権利者の許諾無く個々のデータを利用する行為(複製、譲渡、公衆送信又は公衆送信可能化等)は著作権侵害となり、損害賠償責任(民法第709条)、差止請求(著作権法第112条)、刑事責任(著作権法第119条)の可能性があります。
ただし、複製が私的使用目的の場合は著作権侵害には該当しません(著作権法第30条1項)。
データベースから取り出された個々の情報・データが、例えば、電車の時刻、山の名前と標高、株価データ等の単なる事実である場合は、著作物に該当せず、原則として自由に利用することができます。
ただし、多数のデータがある程度まとまって取り出されたケースであって、(1)創作性を有するデータベースから取り出されたデータ集合体に創作性が再現されている場合と、(2)元のデータベースに創作性が認められないものの、取り出されたデータ集合体が元のデータベースの営業活動を侵害する場合は、法的な制限を受けることがあります。
(1)創作性を有するデータベースから取り出されたデータ集合体に創作性が再現されている場合
著作権法は、データベースのうち、論文、数値、図形、その他情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したものであって、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものを著作物として保護しています(著作権法第2条1項10号、第12条の2)。
例えば、NTTタウンページのデータベースは職業分類体系によって分類されており、創作性があるとされた判例が存在します(東京地裁平成12年3月17日判決・判時1714号128頁)。
(2)元のデータベースに創作性が認められないものの、取り出されたデータ集合体が元のデータベースの営業活動を侵害する場合
創作性を有しないデータベースからデータ集合体を作成した場合について、(a)元のデーターベースが相当の資本を投下して作成されたなど経済的価値を有するものであり、(b)営業活動に用いられている場合であって、(c)当該データ集合体を販売する等の行為が元のデータベースの営業活動を侵害する場合には、不法行為として損害賠償責任を負うものと解せられています。
ただし、この場合でもデータ集合体の複製等の行為については、差止請求は認められないと解せられています(東京地裁平成14年3月28日判決判タ1104号)。
また、データベース提供者とユーザーの間でデータベース利用条件についての契約が成立している場合、ユーザーの契約外での利用行為については債務不履行責任(民法第415条)を追及できるものと考えられます。