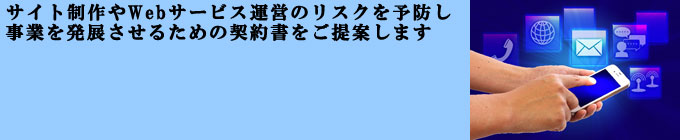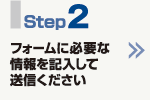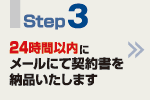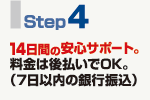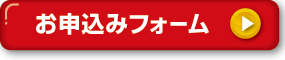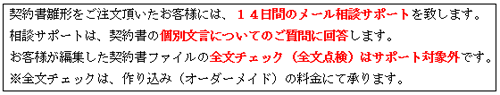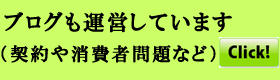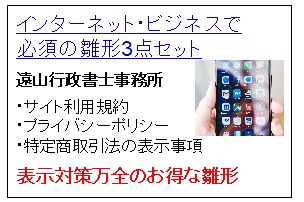経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
ソフトウェアに係る特許権の行使(差止請求、損害賠償請求等)に対して、民法第1条3項(権利濫用の禁止)は適用されるか?
ソフトウェアの特許権の行使に関して、以下のような権利行使があれば権利濫用(のため禁止)と判断される可能性があります。
(ア)権利行使者の主観において加害意思等の悪質性が認められる場合。
(イ)権利行使の態様において権利行使の相手方に対して不当に不利益を被らせる等の悪質性が認められる場合。
(ウ)権利行使により権利行使者が得る利益と比較して著しく大きな不利益を権利行使の相手方及び社会に対して与える場合。
上記の(ア)(イ)は「権利主張の正当性・悪質性の評価分析」によります。(ウ)は「権利行使を認める場合と認めない場合の利益と不利益の比較考量」によります。
これらを総合的に検討し、特許権の権利主張が正当であるか権利濫用にあたるのかを判断することになります。
例えば、「特許権者が権利行使の相手方に対して通常の事業者にとって受忍することができないライセンス契約の条件を強要し、権利行使の相手方が許容できない場合に、その権利行使の相手方に差止請求するなど、特許法の目的である発明の奨励・産業の発達を逸脱し、
相手方に一方的に不利益を押し付ける場合」などは正当性・悪質性の評価分析により権利濫用にあたる可能性が高くなります。
また、「当該特許によって保護される機能がOSやミドルウェア等のプラットフォームとなるソフトウェアの機能である場合、当該機能なくしては当該ソフトウェアのみならず、他のソフトウェアやハードウェアが動作せず、権利行使の相手方や社会全般に大きな不利益が生じる場合」などは利益・不利益の比較考量により権利濫用と判断される可能性があります。
ソフトウェアに関する特許権侵害が生じた場合には、権利者は相手方に対して「差止請求・損害賠償請求・不当利得返還請求・信頼回復措置請求」などの権利行使が可能とされています。
しかし、この権利行使が前述のような権利濫用にあたる場合には、相手方は権利者に対して抗弁を行い、差止請求権等の請求権について不存在確認訴訟を検討することができます。