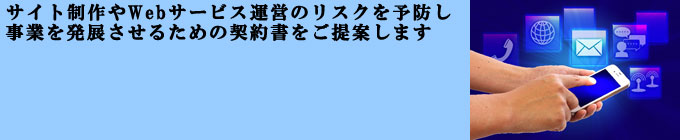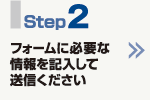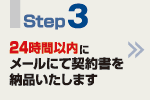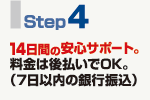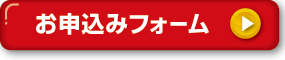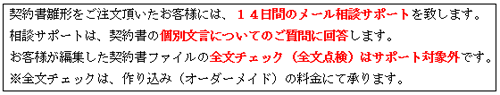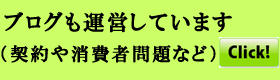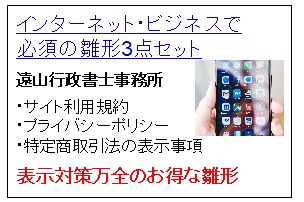経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
無断で、他人のホームページにリンクを張る場合、リンクを張った者は、法的責任を負うことがあるか?
インターネットにおいて、無償で公開された情報を第三者が利用する場合は、著作権の権利侵害にならない限り、原則として自由とされています。
しかし、リンク先の情報を(a)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合、または(b)リンク先に損害を与える目的により利用した場合などでは、不法行為責任を問われる可能性があります。
例えば、リンク先の画像などをリンク元のホームページの一部に取り込んで表示するインラインリンクや、リンク先の情報を丸ごとリンク元のホームページ一部に取り込んで表示するフレームリンクなどについては、以下のような問題が生じる可能性があります。
(1)民法上の不法行為責任
リンク先とリンク元の関係性が誤認され、リンク先のホームページ運営者の名誉が毀損されたりする場合には、(刑法上の名誉毀損罪のほか)民法上の不法行為責任が生じる可能性があります。
(2)不正競争防止法に基づく責任
リンク先の商品表示をリンク元の営業とリンク先の営業とを誤認混同させるようにした場合や、著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用した場合には、不正競争行為に該当する可能性が生じます。
また、リンクを張る際に、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を表示した場合についても同様です。
(3)商標法に基づく責任
リンク元のホームページ運営者がリンク先の他人の商標を無断使用した場合には、その商標の出所表示をしたとしても、商標法上の「使用」にあたると解釈される可能性もあり、そのようなケースでは商標権侵害の問題となることもありえます。
(4)著作権法に基づく責任
リンク先のホームページの情報を、リンク元のホームページの情報であるかのように表示する場合には、著作者人格権侵害等の著作権法違反の問題が生じる可能性があります。
このようなトラブルが頻発している現状を考慮すれば、「無断リンク厳禁」と明示しているホームページにリンクを張る行為は慎重に対応する必要があります。
※平成27年4月の準則改訂により、リンクを張る行為が著作権侵害を助長した場合に関連する裁判例について、以下を追記。
著作権侵害が行われているウェブサイトにリンクを張る行為について、大阪地裁平成25年6月20日判決(判時2218号112頁)は、リンクを張る行為は公衆送信権侵害に当たらないと判示している。ただし、この判例でも公衆送信権侵害の幇助行為としての不法行為の成否が問題とされている
東京地裁平成26年1月17日判決(裁判所ウェブサイト)は、プロバイダ責任制限法上の発信者情報開示との関係で著作権侵害の有無が問題とされた事案であるが、違法にアップロードされた漫画にリンクを張った者のブログでの発言を踏まえて、リンクを張った者が「ダウンロードサーバに本件漫画の電子ファイルをアップロードした者と同一人であると認めるのが相当であり、仮にそうでないとしても、少なくともアップロード者と共同して主体的に原告の公衆送信権を侵害したものである」と認定して発信者情報の開示を認めている。
つまり、著作権侵害や名誉毀損など不法行為が明らかであるようなコンテンツに対してリンクを張る行為は、権利侵害の幇助行為とも受け取られる可能性があり、そのような無秩序なリンク生成は慎まなくてはなりません。