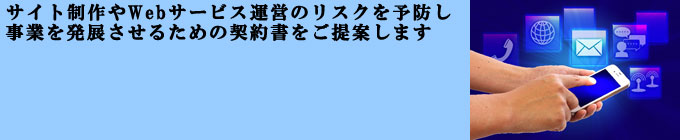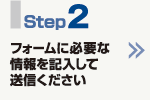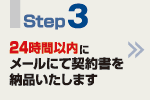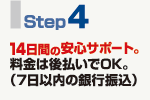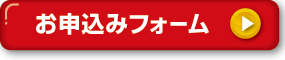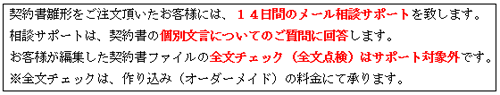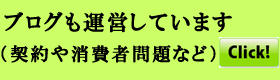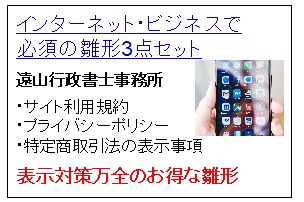経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
「なりすまし」が行われた場合、なりすまされた本人が責任を負う場合があるのか?
なりすましによって行われた意思表示には、原則として本人にはその効果が帰属しません。
しかし、a)本人が行ったように見える外形があり、b)相手方が善意無過失であり、C)本人にも一定の責任があるという民法上の要件を満たせば表見代理の規定(民法109条、110条、112条)によって契約が成立し、本人が責任を負うケースもありえます。
例えば、クレジットカード決済におけるなりすましでは、家族や同居人がクレジットカードを使用した場合や他人にクレジットカード番号等の情報を教えた場合等には、本人が支払い義務を負う可能性が高くなります。
(主なクレジット会社の規約では、クレジットカード会員に①善良なる管理者の注意をもってクレジットカードを管理する義務、②クレジットカードの紛失等については速やかに届出する義務等を定めています。これに反する利用があった場合はクレジットカード会社は支払い義務を逃れます。)