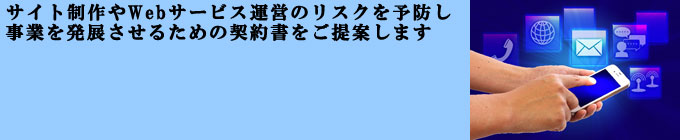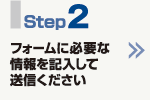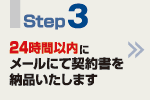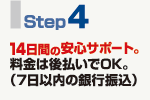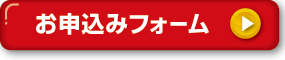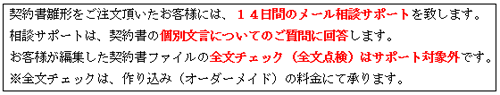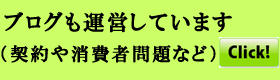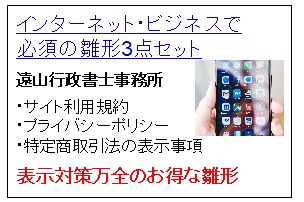経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
外国の消費者が、日本の事業者からインターネットを介して購入した商品を使用したところ生命、身体又は財産に被害を生じたとして、当該商品を製造した別の日本の事業者に損害賠償を請求している。この場合、いずれの国の法律が適用されるか?
外国の消費者が自国の裁判所において、日本の事業者に対して訴えを提起した場合は、訴えが提起された裁判所に国際裁判管轄が認められるかどうかについては、当該裁判所が所属する国の法律によって判断されることになります。
外国の消費者が日本の事業者に対して、日本の裁判所において訴えを提起する場合は、被告の住所地のある日本の裁判所に裁判権が認められます。
日本で裁判が行われる場合については、通則法第17条において、不法行為一般につき、「結果が発生した地の法による」と明記されています。ただし、その地における結果の発生が通常予見することができないものであったときは、加害行為が行われた地の法が準拠法になるとされています。
なお、通則法は不法行為について、第18条に製造物責任に関する特則と、第19条に名誉又は信用の毀損に関する特則を設けており、それらの対象となる不法行為については、第17条の規定に優先して適用されることになります。
通則法第18条の製造物責任の不法行為特則については、生産物で引渡しがされたものの瑕疵により他人の生命、身体又は財産を侵害する不法行為によって生ずる生産業者に対する債権の成立及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法によるとされています。ただし、その地における生産物の引渡しが通常予見できないものであるときは、生産業者の所在地の法によります。
通則法第22条の規定では「不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない」とされており、外国法では懲罰的損害賠償が認められるケースでも、日本法では懲罰的損害の部分については認められない可能性があります。