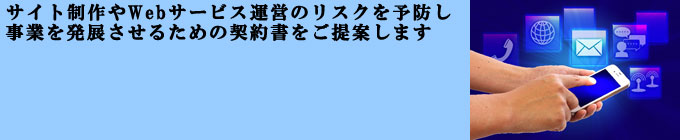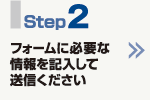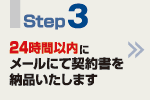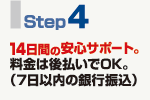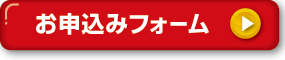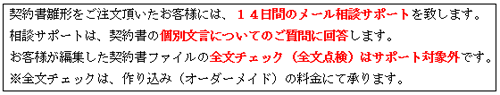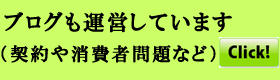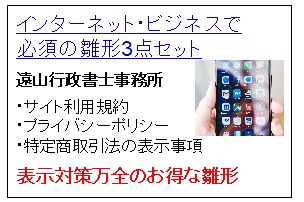経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
共同購入クーポンサービスの取引の構造は、法的にはどのような関係性になるか?
共同購入クーポンとは、一定時間内に一定数がそろえば、購入者が大幅な割引率のクーポンを取得できるビジネスモデルです。この共同クーポンの取引形態には以下の3つの類型が存在すると考えられています。
なお、クーポンについては資金決済法の適用除外とするために、クーポンの有効期限を6ヶ月以内に設定しているところが圧倒的多数を占めます。
(1)債権譲渡
共同購入クーポンは、最低販売数を超える申込があることを停止条件として、加盟店舗でサービスを受けられる権利(債権)とされます。クーポンサイト運営事業者と購入者の間には売買契約が成立します。
店舗がサービス提供を怠った場合には、クーポンサイト運営事業者がその債務不履行責任を負うことになります。
(購入者がクーポンを利用しなかった場合のクーポン代は、クーポンサイト運営事業者に留保されます。)
(2)販売インフラ提供(集金代行)
クーポンを購入した時点で、クーポン購入者と加盟店の間で、加盟店によるサービス提供についての契約が成立します。ただし、最低販売数を超える申込があることが停止条件とされるため、その条件が成就しないと契約は成立しません。
クーポンサイト運営事業者は、クーポンの発行についてのインフラを提供し、さらに集金代行サービスを行う形をとるものが多いです。
店舗がサービス提供を怠った場合には、クーポンサイト運営事業者は債務不履行責任を負わないものと考えられています。クーポンサイト運営事業者の責任については、媒介契約の当事者としての責任もしくはクーポンサイト運営事業者と購入者の間の契約内容によって検討することになります。
(購入者がクーポンを利用しなかった場合のクーポン代は、加盟店に留保されます。)
(3)広告および集金代行
販売インフラ提供型と同様で、クーポンを購入した時点で、クーポン購入者と加盟店の間で、加盟店によるサービス提供についての契約が成立します。ただし、最低販売数を超える申込があることが停止条件とされるため、その条件が成就しないと契約は成立しません。
クーポンサイトに掲載するのは広告に過ぎず、クーポンサイト運営事業者は加盟店から広告料を徴収するとともに集金代行サービスを提供します。
クーポンサイト運営事業者が、広告を掲載しているに過ぎず、契約成立に関しての事実行為を一切行わない場合は、加盟店と購入者の間の契約を媒介しているとは評価できないとされています。
ただし、広告掲載や集金代行の手数料があまりに大きな場合には、クーポンサイト運営事業者も一定の責任を負うものと考えられます。
(購入者がクーポンを利用しなかった場合のクーポン代は、加盟店に留保されます。)
クーポン運営事業者の利用規約の免責条項
クーポンサイト運営事業者の利用規約に「加盟店のサービス内容には一切の責任を負わない」という趣旨の免責条項がある場合でも、購入者が消費者の場合は消費者契約法第8条の「消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し、この利用規約の免除条項は無効とされる可能性が高くなります。
景品表示法の不当表示があった場合
クーポンサイトの表示に優良誤認や有利誤認といった景品表示法の不当表示があった場合には、消費者にサービスを提供するのは加盟店であるのが前提のため、不当表示の責任は加盟店が負うのが原則です。
しかし、クーポンサイト運営事業者が価格決定などクーポン設計にある程度関与する場合は、こうした不当表示が起こらないように配慮する責任は問われる余地はあると考えられます。
当行政書士事務所では、こうした共同購入クーポンサイトについて適正な運営を継続するためのサイト利用規約と加盟店契約書のひな型を販売しております。
この規約と契約書雛形については、下記のリンク先ページをご参照下さい。
>>共同購入クーポンのサイト利用規約と加盟店契約書の雛形<<