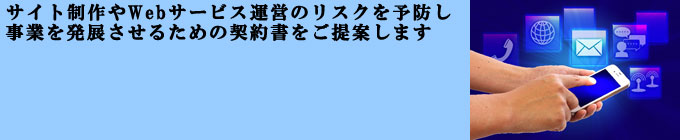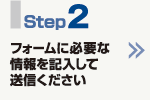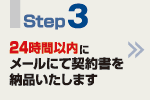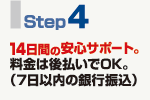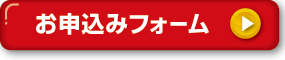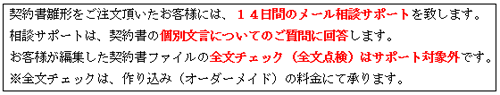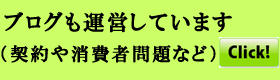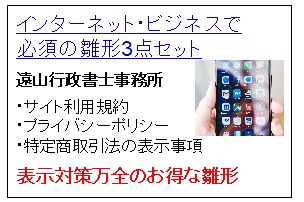経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
プログラムにバグがあったため、動作上の不具合が生じたときに、ベンダーはユーザーに対していかなる責任を負うのか?
プログラムのバグに関するベンダーの担保責任は、基本的にはソフトウェア・ライセンス契約の内容に服することになります。
ベンダーとユーザーがどちらも事業者の場合は、BtoB型の商行為の取引となるので、ソフトウェア・ライセンス契約の特約が優先適用されます。
しかし、ユーザーが一般消費者の場合はBtoC型の消費者契約となるため、消費者契約法の第8条~10条により、民法等と比較して消費者が一方的に不利になる(ソフトウェア・ライセンス契約の)特約は無効とされる場合があります。
例えば、瑕疵担保責任はバグの発見から1年間(民法第566条3項)、債務不履行責任は債務の履行を請求できるときから5年間(商法第522条)とされていますが、これと比較して著しく消費者に不利となる特約の内容は無効と判断される可能性があります。
ライセンス契約のバグの担保責任に関する特約が定めてなかったり、特約が無効とされるケースでは、民法によってベンダーの担保責任を考えることになります。
民法上では、瑕疵(バグ)のあるプログラムを提供したベンダーには問題を解決する責任が生じ、瑕疵担保責任か債務不履行責任(民法第415条)のいずれかが問われます。
なお、瑕疵担保責任には売買の場合(民法第570条)と請負の場合(民法第634条)で参照する条文が異なります。
<瑕疵担保責任が適用される場合>
ユーザーはベンダーに対して、ア)契約解除、イ)損害賠償、ウ)瑕疵修補請求のいずれかを請求することができます。
しかし、契約解除は契約目的が達することができないときに限定されます。また、損害賠償請求についても、ソフトウェアは修正プログラム等で修正することが容易であるという特徴があり、そのような状態においてベンダーの修補対策を拒んで損害賠償請求を行うことは信義則上も認められません。
よって、バグの瑕疵担保責任については、ベンダーによる修正プログラムのリリース等の瑕疵修補の対策が優先されます。
<債務不履行責任が適用される場合>
ユーザーはベンダーに対して、ア)契約解除、イ)損害賠償、ウ)完全履行のいずれかを請求することができます。
契約解除については、ベンダーに対して相当の期間を定めて催告し、これに対してベンダーがその期間内にプログラムの修補もしくは代物提供をした場合には、契約解除は出来ないとされています。
損害賠償については、前述のように修正プログラム等で修正することが容易であるという特徴があり、そのような状態においてベンダーの修補対策を拒んで損害賠償請求を行うことは信義則上も認められません。
完全履行については、民法第415条から修補請求もしくは代物請求が可能とされています。
よって、バグの債務不履行責任については、ベンダーへの修補請求もしくは代物請求が優先されます。