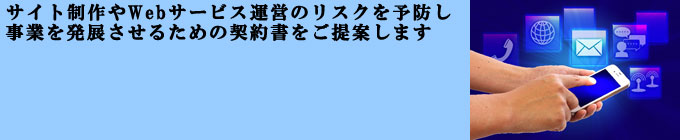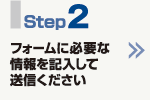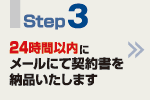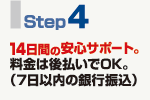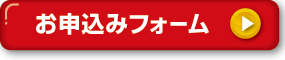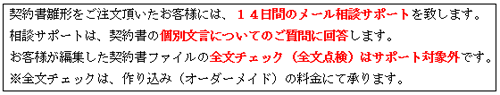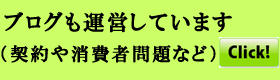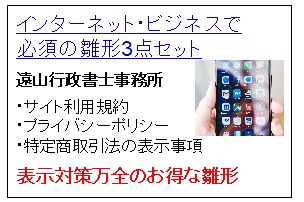経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
日本の消費者が海外の事業者との間で行ったインターネット取引でトラブルが生じた場合、どの国の消費者保護法規の適用を受け、どのように紛争を解決することができるか?
また、逆に、海外の消費者が日本の事業者との間でインターネット取引を行う場合はどうか?
国境を越える消費者と事業者との取引でトラブル(越境消費者問題)が生じた場合には、どちらの国の法律を適用して、どちらの国の裁判手続を行うのかが問題になります。
こうした「事件に適用される法律はどこの国の法律か」という問題は国際私法と呼ばれており、日本の国内法においては、通則法という法律に規定がされています。なお、国際私法は国ごとに定めがあり、その結論が日本と異なる場合もあり、通則法の規定がそのまま絶対的に適用できるというわけではありません。
消費者契約
越境取引であっても、買主が消費者の場合はウィーン売買条約は適用されません。
越境取引の消費者契約のトラブルについては、当該消費者が自らの常居所地の消費者保護規定の中の強行規定に基づく効果を主張した場合は、その強行規定の保護を受けることができます。(通則法第11条1項)
つまり、日本の消費者が海外事業者とのインターネット取引をする場合には、消費者契約法の「事業者の損害賠償責任を免除する条項の無効」(同法第8条)、「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」(同法第10条)、「通信販売における法定返品権」(特定商取引法第15条の2)などを適用すると主張すれば、これらの規定の保護を受けることができます。
どちらの国の法を適用するかの準拠法の定めについては、契約当事者の合意で決めることができるのが原則であり、事前に準拠法の定めがされていない場合は、通則法第8条では商品の売主やサービス提供者の常居所地とされていることから、通常は事業者側の国の法が適用されることになります。
しかし、それでは情報力や交渉力に劣る消費者は、そのまま適用されると消費者にとって過酷な結果になってしまいます。
そこで、前述の通則法第11条1項により消費者契約においては、当事者間の契約上の準拠法の合意よりも消費者保護規定の方が優先するようにされています。
越境取引における消費者保護規定の適用除外
通則法第11条1項の規定では、消費者契約の越境トラブルについては、当該消費者が自らの常居所地の消費者保護規定の中の強行規定に基づく効果を主張した場合は、その強行規定の保護を受けることができるとされています。
この消費者保護規定は、以下の場合には適用除外となり、消費者保護が受けられなくなります。
(1)消費者が自ら海外事業者の所在地に赴いて契約をした場合
消費者が自ら相手方の海外事業者の所在地を訪問して契約した場合は、能動的消費者とみなされ、日本の消費者保護規定は適用されなくなります。
ただし、能動的消費者とは物理的に外国に赴いた消費者を指すものであり、インターネット上で外国の事業者サイトにアクセスする場合は物理的に外国に赴いたものではないため、適用除外にはあてはまらず消費者保護を受けることができます。
(2)消費者契約の債務の全部の履行を海外事業者の所在地で受けた場合
消費者が自ら相手方の海外事業者の所在地を訪問して、その場所で物品を受領したりサービスを受けた場合は、能動的消費者とみなされ、日本の消費者保護規定は適用されなくなります。
ただし、インターネット取引のように、物品が最終的に日本に所在する消費者に送り届けられる場合は、債務の履行地は日本国内となるので日本の消費者保護規定を受けることが可能です。
また、日本の消費者が海外事業者サイトにアクセスして電子データのダウンロードをする場合には、比較的容易な手続であり能動的消費者とまではいえないため、日本の消費者保護規定は適用されると考えられています。
(3)事業者が消費者の常居所地を知らず、かつ、知らないことに相当な理由があるとき
(4)事業者が契約の相手方が消費者でないと誤認し、かつ、誤認したことに正当な理由があるとき
未成年者や成年被後見人などの行為能力について
越境取引については、成年に達する年齢の違いや成年被後見人制度の差異など、国によって行為能力者の制限内容が異なります。
通則法第4条は、行為能力の準拠法を原則として本国法によって定める旨を規定し、例外として、「すべての当事者が法を同じくする地に在った」場合には、本国法では行為能力制限者となるべきときであっても行為地法によれば行為能力者となるときは、行為能力者である旨を規定しています。
例えば、日本の事業者が日本国内で外国の消費者と取引をした場合は、「すべての当事者が法を同じくする地に在った」場合にあたるので、その外国の消費者が自国では行為能力制限者であった場合も、行為地である日本の法律では行為能力者になるべきときは該当消費者は行為能力者とみなされます。
一方、日本の事業者が日本に設置されたサーバー上で外国の消費者と取引をした場合は、「すべての当事者が法を同じくする地に在った」とはいえないので、行為能力の準拠法は原則どおりその外国の消費者の本国の法律に従うことになります。