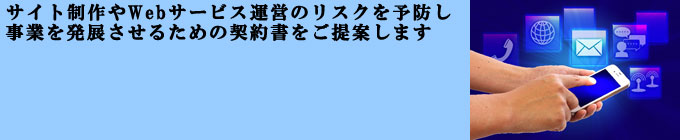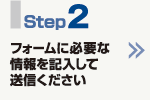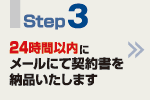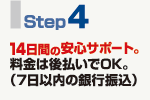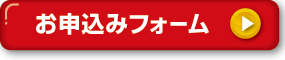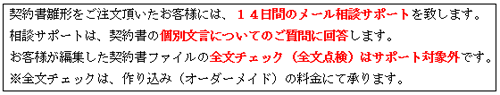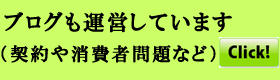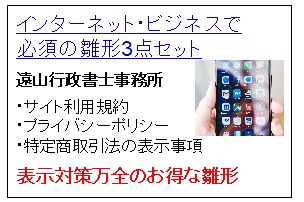経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。
【論点】
日本国内の事業者が外国の事業者を相手にしたインターネット取引においてトラブルが生じた場合に、契約の成立時期や要件、契約履行の考え方など、取引の基本的なルールについては、どこの国の法律が適用され、どのように紛争が解決されるか?
日本の事業者と海外の事業者との取引(越境取引)でトラブルが生じた場合には、どちらの国の法律を適用して、どちらの国の裁判手続を行うのかが問題になります。
こうした「事件に適用される法律はどこの国の法律か」という問題は国際私法と呼ばれており、日本の国内法においては、通則法という法律に規定がされています。なお、国際私法は国ごとに定めがあり、その結論が日本と異なる場合もあり、通則法の規定がそのまま絶対的に適用できるというわけではありません。
(また、当事者の一方の国で判決が確定した場合も、相手方の国で相手方の財産に対する強制執行を行うには、その相手方の国の司法手続を経る必要があります。)
国際裁判管轄と準拠法
日本の事業者と海外事業者との間で契約書(電磁的記録のオンライン契約も含む)を締結している場合、その契約に紛争時の裁判管轄や準拠法の規定がある場合は、その規定が適用されます。(通則法第7条)
例えば、契約書に海外事業者の属する国の裁判管轄を定めていた場合、日本の裁判所では原則として訴えが却下されます。
当事者間で裁判管轄や準拠法を事前に定めていない場合は、当該取引に「最も密接な関係がある地の法」が適用されます。(通則法第8条1項)
「最も密接な関係がある地の法」については、(不動産以外の取引では)当該取引において「特徴的な給付」を行う「当事者の常居所地法」と定められています。(通則法第8条2項、3項)
一般的には、商品の引渡しやサービスの提供が「特徴的な給付」であると考えられるため、原則として日本の事業者が売主やサービス提供者になっている場合は、日本法が準拠法とされます。(これとは逆に、日本の事業者が買主やサービス受益者になっている場合は、海外の法が準拠法となる可能性が高くなります。)
また、契約書(電磁的記録のオンライン契約も含む)に仲裁合意が定めてある場合は、その仲裁合意の内容が優先され、日本の裁判所に訴えを起こしても却下されます。
ウィーン売買条約
国際動産売買については、ウィーン売買条約の加盟国同士の事業者の取引であれば、このウィーン売買条約が適用されます。日本もウィーン売買条約に加盟しています。
ウィーン売買条約の加盟国の事業者と取引をする場合は、買主である外国の事業者からの注文に対し、日本の事業者が承諾の通知を発信し、その承諾が海外の事業者に到達していれば契約は成立したと扱われます。
ただし、以下の場合はウィーン売買条約の適用は除外されます。
a)個人用、家族用又は家庭用にされた物品の売買
b)競り売買
c)強制執行その他法令に基づく売買
d)船、船舶、エアクッション船又は航空機など
※当事者間で締結した契約書に「ウィーン売買条約は適用しない」旨を明記した場合には、この条約の適用はされません。